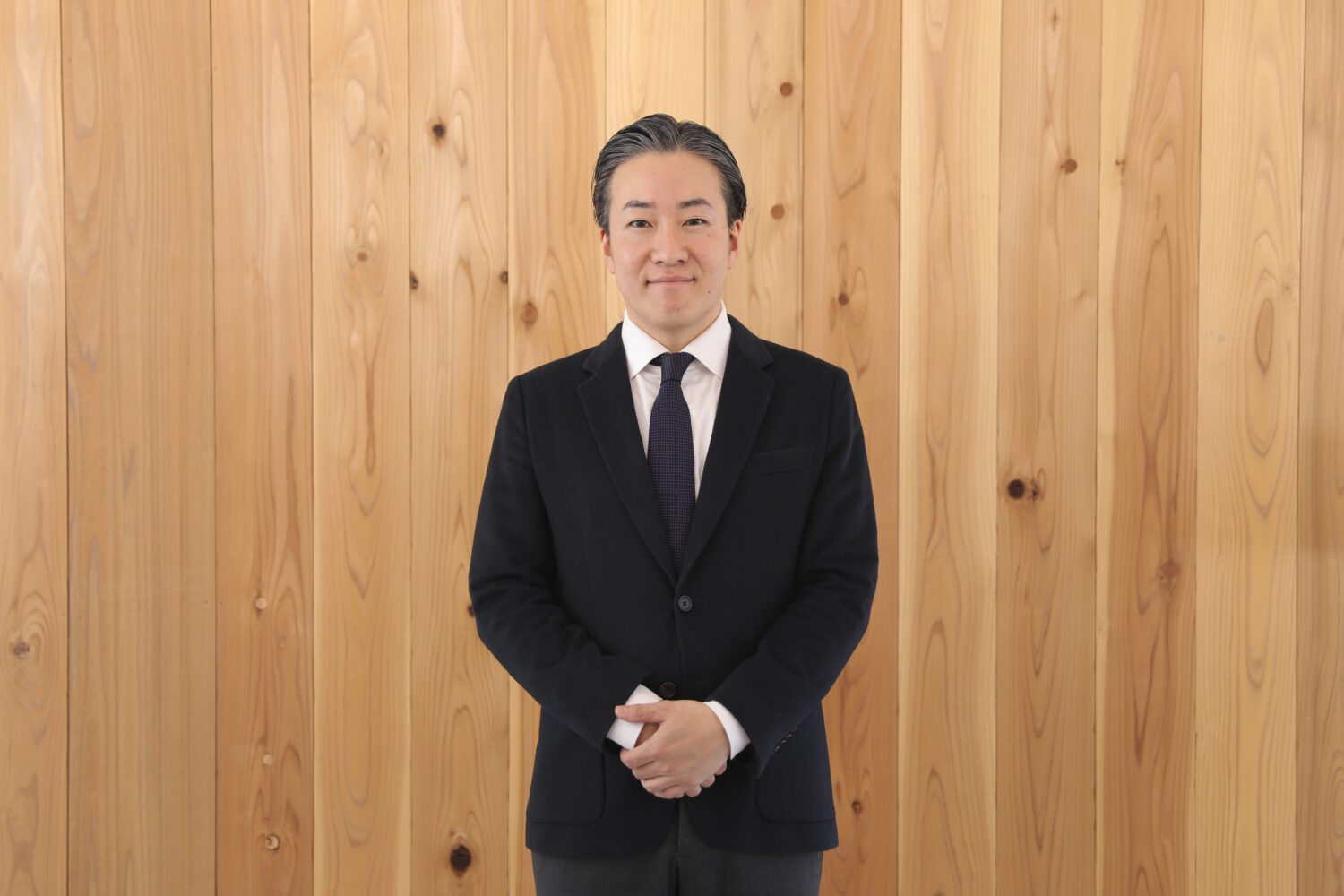新井紙材株式会社の代表を務める新井と申します。
今回は、前後編2回に分けて当社が所属する業界であり、サーキュラーエコノミーを考える上で避けては通れない「静脈産業」について、その構造と課題を紹介したいと思います。普段あまり光が当たることのないこの産業ですが、私たちの暮らしと地球の未来を支える極めて重要な役割を担っています。この記事を通して、そのリアルな姿に触れていただければ幸いです。
日本の廃棄物の現実―年間1,200万トンが埋め立てられている
まず、国内の廃棄物の現状からお話しします。2019年度、日本国内で排出された廃棄物の総量は約4億5,000万トンにのぼります。このうち、最終的に埋め立て処分された量は約1,200万トン。割合にすると約3%です。
この「3%」という数字だけを見ると少なく感じるかもしれませんが、1,200万トンという質量は凄まじい量です。私たちが日々向き合っている廃棄物の現場では、例えば下記の画像で約10トン程度です。その120万倍もの量が、毎年日本のどこかに埋められているのです。

埋め立てが行われる最終処分場は、山に穴を掘り、そこに廃棄物を積み上げていく場所です。一度こうなってしまえば、その土地の生態系が元に戻ることはありません。さらに、埋め立てが終了した後も50年間は管理し続ける義務がありますが、50年が過ぎれば安全という保証はどこにもないのが実情です。これは環境破壊以外の何物でもなく、いかにしてこの量を減らしていくかが国家的な課題となっています。

廃棄物は大きく2種類に分けられます。企業活動から出る「産業廃棄物」と、私たちの家庭から出る「一般廃棄物」です。排出量は産業廃棄物が約4億トンと圧倒的に多い一方で、埋め立てられる比率(最終処分率)を見ると、産業廃棄物が約2%なのに対し、一般廃棄物は約10%と、家庭ごみの方が高くなっています。ここにも構造的な課題が隠されています。
世界が注目する日本の「中間処理」―97%を減らす技術
では、排出された廃棄物はどのように処理されるのでしょうか。フローは「排出」から始まり、「収集運搬」、そして「中間処理」を経て、「最終処分」へと至ります。
ここで最も重要なのが「中間処理」です。排出された廃棄物がいきなり埋め立てられるわけではありません。必ずこの中間処理施設を経由します。ここで何が行われるかというと、「選別」「圧縮」「破砕」「焼却」「脱水」などです。

例えば、様々なものが混ざった廃棄物を素材ごとに「選別」し、かさばるものを押し固めて「圧縮」します。古紙や一部の廃プラスチック等は、この時点でリサイクル原料として売却可能となり、再生資源を必要とする業者によって再資源化され、これがいわゆる「リサイクル」と言われている処理です。
また、焼却も中間処理の一種で、燃やすことで体積を大幅に減らす「減容」を目的とします。水分を多く含む汚泥などは「脱水」することで重量を減らします。
こうしたリサイクルや減容処理によって、最終的に埋め立てられる量を総排出量の約3%にまで抑えているのです。つまり、97%はこの中間処理の段階で資源化されたり、減容されたりしているわけです。この高度な中間処理技術こそ、日本の静脈産業が世界に誇る素晴らしい成果であり、海外からも大きな注目を集めています。
一方で、一般廃棄物を中心に焼却処理が非常に多く、そのCO2排出量も相当のものであることから、国際的な批判を浴びていることも事実です。特に使い捨てプラスチックの多さとリサイクル率の低さは国としても頭を抱えている課題です。焼却処理は衛生的で効率的ですが、再資源化可能な生ごみや紙類、プラスチックが大量に燃やされてしまっているのも事実です。
繰り返しになりますが、1,200万トンという質量は決して少なくありません。米国や中国といった大国と比べると微々たるものですが、一度中間処理施設や最終処分場を訪れると、その圧倒的な物量に考えさせられることは少なくないと思います。
当社ではさまざまな廃棄物処理現場のご案内をしておりますので、ご興味があればぜひお問い合わせください。